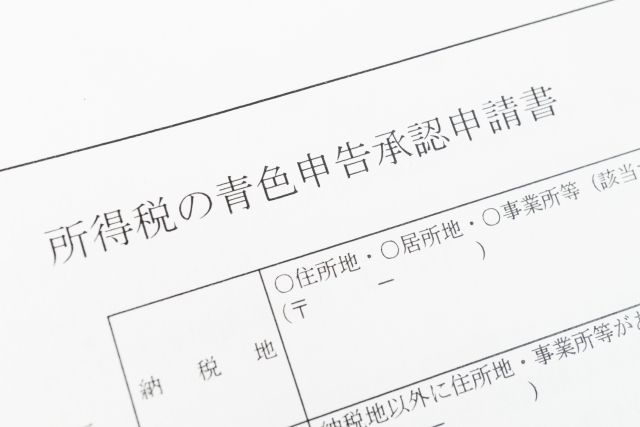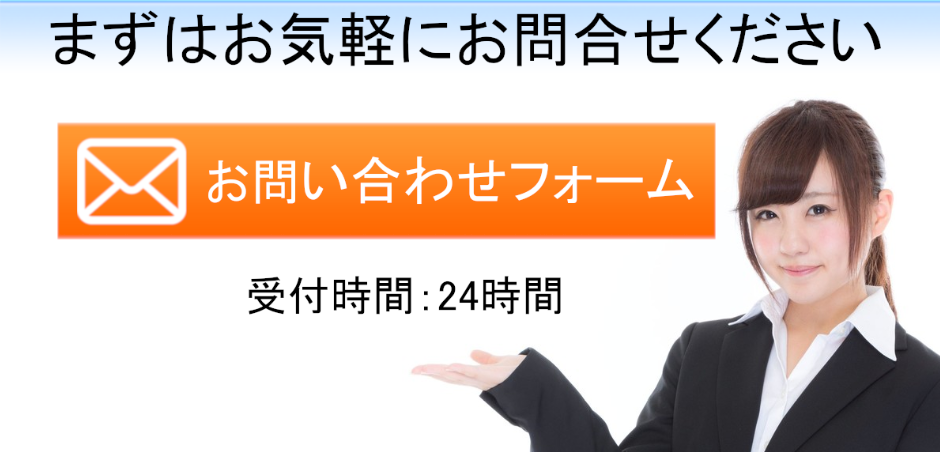公認会計士と税理士って何が違うのですか?
そんな疑問を持っている方のために、公認会計士と税理士の違いについてご説明します。
公認会計士と税理士の業務の違い
| 公認会計士 | 税理士 | |
| 対象の会社規模 | 主に上場企業などの大企業 | 主に中小企業 |
| 業務内容 | ・会社の作成した決算書に間違いがないかチェックする
・コンサルティングなど |
・税務申告書の作成や、税務相談など |
まず初めに、一般的な公認会計士と税理士の業務に関する違いをご説明します。
公認会計士の業務は、上場企業などを中心に、会社が作成した決算書に間違いがないかをチェックするのが仕事です。
また、新規上場(株式公開)に向けた社内体制の構築にかかわるコンサルティングなどを実施したりもします。
税理士は、税金の専門家です。
中小企業などを中心に税務申告書の作成や税務相談などを実施します。
大手の会計事務所では、税理士でも上場企業を相手に税務業務を実施します。
公認会計士であることの強みについて
丸山大介公認会計士・税理士事務所は、長野市でも数少ない公認会計士と税理士の資格を持っている会計事務所です。
それでは、通常の税理士と比べて公認会計士であることの強みをご紹介したいと思います。
経営上の意思決定に役立つ「管理会計」に強い
公認会計士は、経営上の意思決定をする際に役立つ「管理会計」の知識に優れています。
例えば、
- 毎月の利益を出すためにどれ位売上が必要かわかりますか?
- 新規店舗を出店するときに、設備投資としていくらまで使って大丈夫かわかりますか?
- 会社にお金が残らない理由がわかりますか?
- どの商品を優先的に売ると利益が最大化するかわかりますか?
管理会計はこれらの答えを出すために必要な情報を得る事のできるものです。
したがって、これらの知識を活用しながら、経営に関するアドバイスが可能です。
なぜ公認会計士が管理会計の知識に優れているのかというと、資格を得る際に管理会計を専門的に勉強しているからです。
税理士の資格を得る際は、管理会計の知識は要件とされていません。
経営学を知っている
公認会計士は、経営学に関する基本的な知識を持っています。
経営戦略やマーケティング、組織設計などにかかわる知識があるため、経営戦略を立案する上での基本的なアドバイスも可能です。
※経営学は、公認会計士によって勉強している人としていない人がいるため、すべての公認会計士に共通しているわけではありません。
事務所代表の丸山は、経営学を勉強して公認会計士の資格を取得しています。
税理士の資格を得る際は、経営学の知識は要件とされていません。
会社の仕組み作りに強い
公認会計士は、社内の仕組みを作る知識にも優れています。
例えば、
- 受注→生産→納品→請求→資金回収といった、販売にかかわる仕組み
- 発注→検収→支払いといった、仕入にかかわる仕組み
- 現金や在庫、固定資産などといった、会社の資産管理にかかわる仕組み
- 経費の精算などにかかわる仕組み
公認会計士は、このような仕組みにかかわる知識をもっているため、成長中の会社が社内の体制を整えるときにアドバイスが可能です。
上場企業などの大企業は、上記に記載されているような社内の仕組みについて、適切に作られ運用されているか公認会計士のチェックを受けないといけません。
したがって、複数の上場企業の社内体制を知っている公認会計士だからこそ提供できる価値になります。
会社運営のルールを定めた会社法の知識がある
会社法とは、会社の設立から解散、株主総会や組織運営、株式・社債等の資金調達など、会社を運営するためのルールを法律としてまとめたものです。
公認会計士は、会社法を専門的に勉強してこるとから、会計や税務に関する会社法の扱いに優れています。
知らない間にコンプライアンス違反となっていたケースも少なくありませんので、適法に会社運営を行うためにも会社法の知識は必須です。
税理士については、資格を得る上で会社法の知識は要件とされていません。
公認会計士の強みまとめ
公認会計士であることの強みをまとめます。
- 経営上の意思決定する際に役立つ「管理会計」に強い
- 経営学を知っており、経営戦略を立案する時の基本的なアドバイスが可能
- 成長中の会社の仕組み作りに強い
- 会社法の知識があるため、コンプライアンスを遵守しやすい
もしあなたの会社が急成長していたり、今後大きく成長させることを望んでいるのであれば、公認会計士・税理士の資格を持った会計事務所を選ぶことで、税理士としてのサービスに加え、上記のようなメリットを得る事ができるでしょう。
弊事務所のサービスにご関心がある場合は、是非一度お問い合わせください。